森と君と+呪いたち
1ページ/7ページ
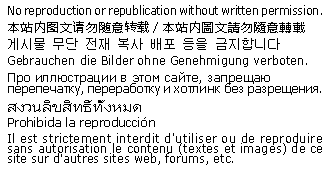
・・・・・・・・・・・・・・・

迷った木々のなか 「遊ぼうか」 と声がした。
0
「……暑い」
思わず、口からそれが出てしまう暑さだった。そんな小さな呟きも、生ぬるく吹き込んだ風にかき消される。
今の視界には、自分の歩いている坂道と、夏の陽射しを浴びて力いっぱい生い茂る、緑。それだけ。
同じような道が続く中、さっきから、歩きっぱなしで、疲れてきた。
「うーん……もう、着くはずだけど」
目的地は、歩いて行かねばならず、自分の《10歳の足》では、わりと長く感じる距離なのだった。
歩みを一旦止める。
肩にかけているペットボトルを掴むと、入っていた茶を少し飲んだ。
これもまた、生ぬるい。飲み干して、キャップをしめると、小さく息を吸う。少し、楽になった気がして、また歩き出す。
もう少しだと言い聞かせながら、だんだん急になっていく斜面を息を切らして進んでいくと、ようやく目的地の丘の上に到着だ。
叫びたい気持ちが沸き上がったが、堪える。丘の下には、きらきらと陽射しを浴びて輝く向日葵畑が広がっていた。そうだ、これが見たかったのだ。時折風に揺れ、輝く美しい花の色を見ることで、ようやく、セイは一年で最も暑い季節の到来を感じることが出来る気がした。だから、毎年、最低でも一度は、向日葵が咲く頃に、できる限りここに来ているのだ。
向日葵と自分を隔てる柵の前に座り込み、目を細めていたときだった。
「あー、ここにいたのー」
後ろから急に声がした。呆れたような、最初から確信していたような響きを持つ、はきはきした中性的な声だ。
「ひっ!」
びっくりして短い悲鳴をあげてみたが、聞き馴染みのある声だったので、なんだお前か、と呟いた。振り向かない。
「おっかしー。なぁにびびってんの? せっかくドゥロロが、わざわざ追いかけて来てくれたのに」
「上からだな。そりゃどうも。何の用?」
「ひどーい、そんな、さらっと! 遊びに来たら居なくって、心配して探しに来てみたんだよー」
「母さんが、だろう」
ドゥロロは、家の前のマンションに住む少年だ。
いつもとても明るい。
彼のいつも楽しげに笑うところは、ひそかに気に入っていた。
本当はぼんやり向日葵を見ていたいというのに、気が散るほど、何かをぺらぺら話しかけてくるので、しかたなしに振り向く。
普段はワンピースのような服を着ているのに、今日はなぜか甚平のような服を着たドゥロロが、にこにこと笑いながら、両手で重そうにバケツを持っていた。オレンジ色の短めの髪は、少し濡れて、キラキラしているようだ。
「やあっ、セイー」
「……やあ。また魚、とってたの」
バケツをのぞきこむと、細身の、白い体の魚が、10匹ほど入っているのが見えた。
「うん、セイも食べるだろう? おばさん、天ぷら作ってくれるってー」
「おー、やった」
ドゥロロは一人で暮らしている。家族でもない。
だが、四年ほど前から、時折、母とセイが住む家の食卓を共にするようになった。
なんとかのよしみ、というやつなのか、気が付けばそうなっていた。
セイはほとんど、彼のことを知らなかった。
さまざまな疑問が残っているが、聞こうとするたびに、適当にはぐらかされている。
それでも、なぜだかドゥロロには警戒心を持つことが出来ないのだ。なぜか、受け入れてしまっていた。
天ぷらのことを聞き、喜んでみせると、ドゥロロは本当に嬉しそうに笑った。こちらまで嬉しくなってしまう。
「だから、早く帰ろー?」
「わかったよ、ちょっと待って」
ポケットに入れていた、小さなカメラで、向日葵畑の写真を撮ってから保存する。
「これで、よし」
満足げに笑うセイを、ドゥロロはしばらくきょとんと見つめていたが、写真を撮り終わったことに気付くと、にっと笑みを作った。
「じゃ、行こう」
「ああ」
家につくまでの間、互いに特に何も言わなかった。
(――この距離感、とでもいうのだろうか。特別仲が良いわけでも、悪いわけでも、友達でも、家族でも、親友でもない、けれど)
関係性でわざわざ固定せずとも、ただ、そばにいられるこの感じが好きだった。
出来るならずっと続いて欲しいと、願ってしまう。
「ただいまあー」
ドゥロロが、バケツを置いてから、靴を脱ぐ。
そして玄関の、普段、訪れた客が座って話をしたりしている場所へ、倒れ込んだ。
(玄関というのは、どうしてこう、ひんやりしているのだろうか)
セイも同じように横になってみた。火照った体には、ひんやりした木の感触が気持ち良かった。